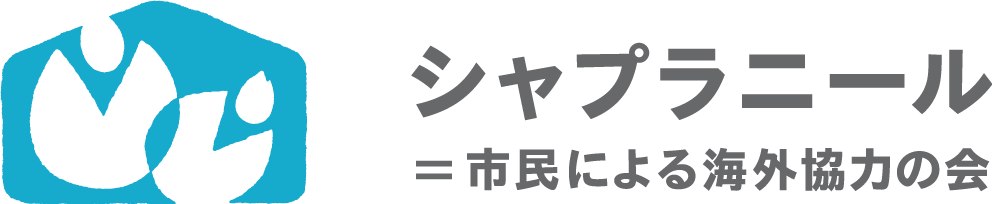取り残された問題
バングラデシュには他人の家で家事使用人として1日中、働く少女たちがいます。
彼女たちには学校で学ぶ、友達と遊ぶ、そんな子どもらしい時間はなく、
外部の人の目に触れない家の中で、人知れず権利を奪われています。
バングラデシュには他人の家で
「家事使用人」として1日中、
働く少女たちがいます。
彼女たちには学校で学ぶ、友達と遊ぶ、
そんな子どもらしい時間はなく、
外部の人の目に触れない家の中で、
人知れず権利を奪われています。
問題の裏側
国際労働機関(ILO)の報告では、バングラデシュには家事使用人として働く少女が数十万人いるとされています。彼女たちは、外からの目が届かない屋内で働いていることから、適切な衣食住を得られない状況に置かれたり、性的被害を含め暴力を受けたりすることもあります。少女たちは教育の機会、健やかに成長する、子どもの権利を奪われています。

少女たち
家庭の厳しい経済状況が理由で仕方なく働いている少女が多い。幼いうちから学校で学んだり同年代の子どもたちと交流する機会がないため家事使用人以外の自分の可能性を想像できない状態にある

親・雇い主
「児童労働」が子どもの権利を奪っているという意識を持っていない人も多い。おとなに比べ、家の人とトラブルを起こすことも少ない、安価で雇える等の理由で少女を家事使用人として雇う。保護者は、娘はいずれ結婚し、息子が自分たちの面倒を見るという考えから、娘を安易に働きに出させる傾向がある。

バングラデシュ社会
2015年に政府が政策を採用し、家事使用人の総合的な福利の保障を目指し、家事を“労働”として認めたが、問題意識が社会全体に浸透しきれておらず、また家事使用人として働く子どもという児童労働としての認識が弱い。
シャプラニールの取り組み
ダッカ市内で支援センターを設け、少女たちに基礎教育や縫製等の技術研修を実施。
また、雇い主や保護者への訪問と地域住民への意識啓発を行うことにより、
少女たちを取り巻く人々の行動変化を促していくとともに、
「家事使用人保護および福祉政策」が法制化され適切に実施されるよう政府、行政へ働きかけます。
少女たちの送り出し地域である農村部では、保護者、学校等への意識啓発を行います。
ダッカ市内で支援センターを設け、少女たちに基礎教育や縫製等の技術研修を実施。また、雇い主や保護者への訪問と地域住民への意識啓発を行うことにより、少女たちを取り巻く人々の行動変化を促していくとともに、「家事使用人保護および福祉政策」が法制化され適切に実施されるよう政府、行政へ働きかけます。少女たちの送り出し地域である農村部では、保護者、学校等への意識啓発を行います。
少女たちへの取り組み
ダッカ市内で2つの支援センターを運営し、ベンガル語や英語などの読み書き、計算などの基礎教育、また、思春期の身体の変化や性暴力をいかに防ぐかを学ぶ性教育や、病気を防ぐ衛生教育などを提供しています。また、就業体験として縫製の技術研修や料理教室、絵や歌・踊りなどを楽しむレクリエーション、運動会や文化祭などを実施しています。

雇い主や親への取り組み
雇い主やスラムに暮らす、少女の保護者への家庭訪問を継続し、労働環境の確認や学校への編入の働きかけを行っています。雇い主や保護者に対し、子どもの権利に関するワークショップを開催するなど、児童労働による弊害や教育の大切さを伝えています。

地域社会への取り組み
支援センター周辺の地域住民が家事使用人として働く少女を児童労働として認識し、子どもを雇わない意識を地域内に広げていくための意識啓発を行います。自治会のような組織を通じ、子どもの権利や法制に関するワークショップを開催し、地域の学生が子どもの権利について考えたり、少女たちの学校編入への協力を呼びかけています。また、地域の警察や行政機関とも連携し、地域住民が少女への暴力などの発見時に適切に通報、対応できるようにしています。

行政への取り組み
行政機関への定期的訪問、住民と郡や村などの行政関係者とのワークショップに取り組みます。また、2015年末に閣議決定された「家事使用人の権利保護および福祉政策2015」が法制化されるよう、労働雇用省大臣との話し合いの場を作るなど、行政へのアドボカシーに力を入れています

バングラデシュ社会への取り組み
家事使用人として働く少女に関するシンポジウムを開催し、NGO、国際機関、各省庁とのネットワーク構築を行います。また、新聞やテレビなどメディア掲載や広告を出稿し、家事使用人に関する問題意識を広めます。またバングラデシュで児童労働をなくすためのNGO・団体のプラットフォームを設立し、国内の他団体とともに問題の根本解決をめざします。

送り出し地域での取り組み
多くの少女が都市部へ働き出されているマイメンシン県の農村部にて、少女たちの送り出しを抑止するために、保護者や学校、地方行政を対象とした児童労働の意識啓発や学校中退防止の取り組み等を行います。

これまでの成果
2024年度に支援センター(2カ所)を開設。地道な家庭訪問などで雇用主や保護者に呼びかけ、43名の少女が通っています。
(2024年度)
技術研修を受講した少女の74%が研修で得た技術を活かし、少額の現金収入を得られるようになりました。その中には仕立職人として自立した少女もいます。 <関連記事>
(2023年度)
勉強の得意な少女10名が支援センターでチャイルドリーダーとなり、先生のサポート役として授業を行うようになりました。<関連記事>
(2023年度)
活動の様子
photo gallery

家事使用人として働く少女 
家事使用人として働く少女 
実態調査のために雇用主宅を訪問する現地スタッフ 
支援センターで学ぶ少女たち 
支援センターで学ぶ少女 
技術研修を受ける少女たち
video
report
企業・団体との協働
さまざまな企業や団体からの寄付、物品寄付「ステナイ生活」の支援、
現地の事業への直接支援などでご協力をいただいています。
企業のSDGs、CSR活動についてのお問い合わせはこちらをご覧ください。
さまざまな企業や団体からの寄付、
物品寄付「ステナイ生活」の支援、
現地の事業への直接支援などで
ご協力をいただいています。
企業のSDGs、CSR活動についての
お問い合わせはこちらをご覧ください。
プロジェクト詳細
| プロジェクト正式名称 | (1)家事使用人の少女の権利を守るプロジェクト(支援センター運営、地域住民への啓発活動) (2)家事使用人の少女たちに素敵な未来をキャンペーン(アドボカシー活動) |
| 活動期間 | (1)2024年5月〜2026年3月 (2)2013年~ |
| 活動地域 | (1)ダッカ市・マイメンシン県 (2)ダッカ市・全国 |
| 裨益者数 | (1)約2470人 (2)不特定多数 |
| パートナー団体 | (1)ASD 1988年設立のNGO。ダッカ市内のスラムでの支援活動を専門として活動していた。徐々に他の都市や農村部でも開発プログラムを行うようになり、現在は、子どもの権利、健康・栄養、WASH、防災など幅広い分野で活動。 (2)パートナー団体無し(シャプラニールダッカ事務所単独プロジェクト) |
あなたにできることが、必ずあります。
あなたにできることが
必ずあります。
「誰も取り残さない社会」、その実現へ。
シャプラニールと一緒に、アクションを起こしませんか。
「誰も取り残さない社会」その実現へ。
シャプラニールと一緒に、
アクションを起こしませんか。
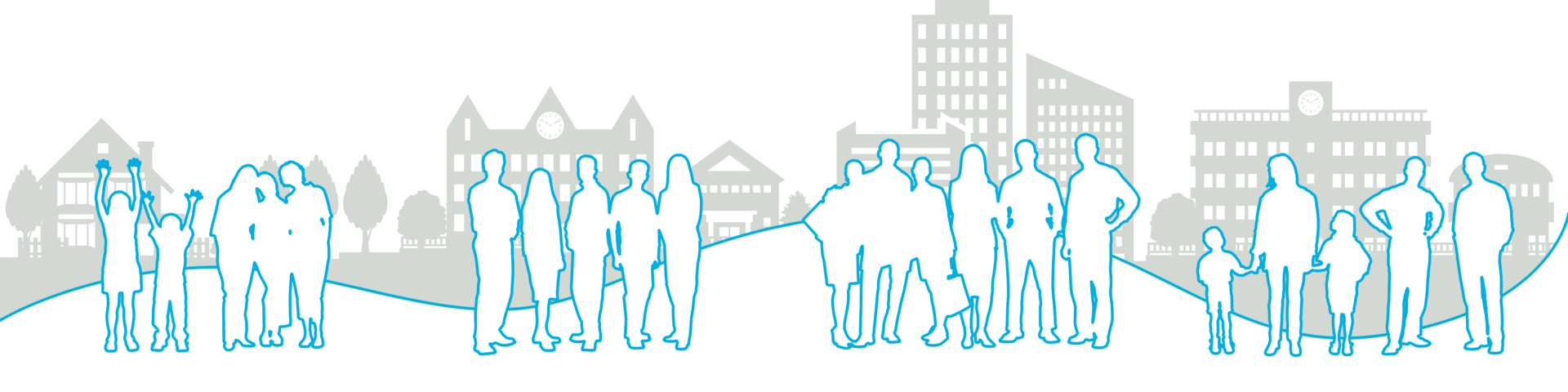

シャプラニールの支援活動一覧
1. 子どもの明日を守る活動
2. 災害に強い地域をつくる活動
3.社会からの孤立を防ぐ活動
4.市民どうしのつながりを促す活動